日の出文書
- SAPO(部門責任者)

- 2024年11月7日
- 読了時間: 7分
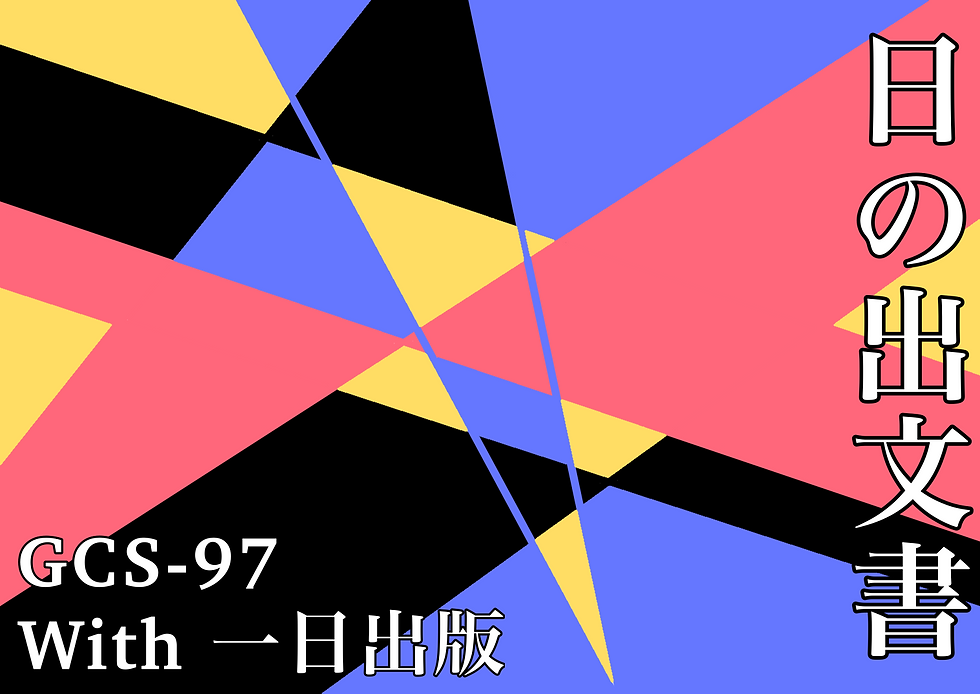
輝く新生活
今日は新緑が生い茂る穏やかな日だ。澄んだ青空の下、柔らかい春の風が吹き、新しい生活の幕開けにぴったりの気候だった。そして、まさにこの日に私は高専に入学する。新しい制服に袖を通しながら、これから始まる学生生活を思うと、胸が自然と高鳴った。
期待もあるが、正直不安も大きい。小中学校の頃とは違い、勉強も専門的になると聞いている。特に数学や物理といった理系の科目は苦手意識があったため、果たしてちゃんとついていけるだろうか。
まだ何も始まっていないのに、いろいろなことが頭の中をぐるぐると駆け巡る。でも、今日がその第一歩だ。とにかく、今日という一日を大切に過ごそうと自分に言い聞かせ、家を出た。
校門をくぐると、緑に囲まれた校舎が目の前に広がっていた。新しい場所に来たんだと改めて実感し、気持ちが少し引き締まる。入学式では、同じ制服を着た新入生たちが集まり、少しよそよそしい雰囲気が漂っていた。
皆、顔に不安と期待が入り混じった表情を浮かべていて、それを見て少しホッとした。私だけじゃないのだと思うと、勇気が湧いてきた。
式が終わり、いよいよ教室に向かう。新しいクラスメートとの出会いに少し胸が躍るが、どんな人たちがいるのか全く想像がつかない。教室に入ると、まず目についたのは、それぞれの個性が光る学生たちだった。
制服の着こなしや髪型、表情など、一人ひとりがどこか独特で、これまでの学校では見たことがないタイプの人が多かった。少し驚いたが、逆にそれが「高専らしい」のかもしれないと思うと、妙に納得もした。
教室の中ほどに座り、周りをキョロキョロと見渡していると、隣の席に座っていた男の子が視線を合わせてきた。思い切って話しかけてみると、彼も少し緊張した表情を浮かべていた。「君も緊張しているんだ?」と聞くと、彼は少し照れ臭そうにうなずいた。
私も「実はこっちもだよ」と言うと、彼は少し笑顔を見せてくれた。その瞬間、どこかほっとするような気持ちが広がり、初対面のぎこちなさが和らいだ気がした。
話を聞くと、彼は少し遠くの地域から来たらしい。親元を離れ、一人暮らしをしながら通うという。私とはまた違った形で不安もあるだろうが、それでも新しい生活に挑戦しているその姿勢に、少し勇気をもらった。
「これからお互い頑張ろうね」と軽く励まし合いながら、新たな友達ができた喜びが心を温かくしていくのを感じた。
授業が始まり、最初から専門的な内容に圧倒された。特に先生が熱弁を振るう数学や物理の話が、少し難しそうで不安がよぎる。友人も同じような表情をしていて、それが少し心強かった。
「これから大丈夫かな」とつぶやくと、友人も同じ気持ちだったらしく「まぁ、なんとかなるだろう」と苦笑しながら答えた。その言葉に私も「確かに、なんとかなるよね」と笑い返し、少し肩の力が抜けた気がした。
長い一日が終わり、帰り道、今日のことを振り返った。初めての授業は難しかったし、クラスの雰囲気にもまだ慣れていない。
でも、それでも今日一日で新しい友達ができたことは、大きな収穫だと思う。不安ももちろんあるが、「頑張ろう」という気持ちが自然と湧いてきていた。これからどんな日々が待っているのか分からないが、少しずつ自分のペースで前に進んでいこう。
そんなことを考えながら家に帰り、一日の疲れが一気に押し寄せてきた。布団に入り、明日も頑張ろうと心に決めて目を閉じると、次第に眠気がやってきた。
さて、今日はここまでにしようか。
山と私の人生観
山登りが趣味となったのは、もう何年も前のことだ。最初は仲間たちに誘われて半ば強引に連れて行かれたが、気づけばすっかり山の魅力にとりつかれていた。
登るたびに感じる清々しい達成感、目の前に広がる壮大な景色、そして何よりも自然と向き合う時間が、日々の雑多な思いから私を解き放ってくれる。登山を重ねるうちに自分でもいつしか、標高の高い山に登るほど「より良い登山者」だという、ある種の思い込みが心のどこかに染みついていたように思う。
そんなある日、ふと新聞の記事を眺めていると、「日本で最も標高の低い山」として、ある山が紹介されているのを見かけた。普段ならスルーしていたかもしれない。しかし、その日私はなぜかその記事に惹きつけられ、ふと心の中に芽生えた好奇心に素直に従った。
記事によると、その山は「山」と呼ばれるものの、実際の高さは驚くほど低く、どちらかといえば丘に近いようだった。標高は数十メートル程度、私がいつも登っている讃岐富士のような堂々たる姿とは程遠いものだった。
だが、どういうわけか「一度登ってみよう」という気持ちが湧き上がり、私は次の休みにその山を目指すことを決めた。
それから2か月が経ち、ようやくその山へと向かう日がやってきた。心の中には軽い興奮と同時に、どこか「なぜこんな低い山に登るんだろう」という自問が浮かんでいた。
登山家として、なぜこれほど低い山に興味を持ったのか。登山道具も、いつもの大掛かりなものは必要ないだろうと身軽な装備で家を出た。いつもなら重装備で山頂に挑むところだが、今日の登山はどこか遠足のような気軽さが漂っていた。
その山は、地図で示されている通り本当に小さな山で、登山道と呼ぶのもためらわれるほど緩やかな道が続いていた。山といえば険しい岩場や長い道のり、急な傾斜をイメージしていた自分にとって、その道はまるで公園の散歩道のようだった。何とも物足りないと感じつつも、意外とそれが新鮮で、気づけばゆっくりと歩を進めながら周囲の景色に目を向けていた。
山道は整備されており、周囲には鮮やかな草花が風に揺れている。登るうちに、不思議と気持ちが穏やかになり、いつも感じる「登頂しなければ」という焦りが消えていった。自分が歩いている山道は確かに小さな山である。
だが、よく目を凝らしてみると、山を覆う緑や足元に咲く花々の生命力が、それぞれの輝きを放っているのに気づいた。
ようやく山頂に到着したが、そこは見渡す限り広がる眺望があるわけでも、息をのむような絶景が広がっているわけでもなかった。しかし、ひときわ青く澄んだ空が広がり、風が心地よく私の頬を撫でた。
その小さな山は、背丈が低いなりに、空に向かって堂々と伸びているようだった。どれだけ低くても、自らの高さに誇りを持って、まっすぐと立っている。標高の高い山々と比べれば、その存在は小さく見えるかもしれないが、この山もまた確かに「山」なのだと気づいた。
それまでは、安いものより高いもの、良質なものがすべて良いという価値観があったように思う。標高の高さも、登山者としてのステータスのように思っていたが、この小さな山を登っていると、そんな価値観がゆっくりと崩れていくのを感じた。
高い山には高い山の、低い山には低い山の、それぞれの価値がある。そして、その価値は他と比べられるものではなく、その山がただそこにあることで、ただそこに生きていることで成り立つものなのだと感じられた。
この山を登りながら、ふと自分の人生について考えさせられた。今までは自分も、社会の中で「より高いもの」を目指さなければならないと思っていた。
良い会社に入ること、より高い給与を得ること、世間的な成功といった「高いもの」を追い求め、得られるものが多ければ多いほど価値があると信じていた。だが、この小さな山と向き合っていると、そんな考えが実に狭いものであると気づかされた。
人生にはさまざまな生き方がある。必ずしも高い山を目指すことだけが価値ではない。自分のペースで、私自身の高さで生きていくこともまた、一つの価値であり、誇りを持ってよいことなのだ。
この山も、他の高い山々と比較されることなく、ただ自然の一部として存在している。その姿は、何かに怯えることもなく、ただそこに立ち続けているように見えた。
「私も私なりの生き方で、胸を張って生きていこう」
小さな山を見上げながら、そう心の中でそっとつぶやいた。それは、山登りが趣味となって以来、初めて得られた「高い山」を目指すことだけがすべてではないという新たな視点だった。そして何よりも、その小さな山が私に教えてくれたものは、どんな場所にいても、どんな背丈であっても、その場所で自分らしくあることが一番の強さであるということだ。
山を下る足取りは軽く、心の中に一つの「登頂」のような達成感があった。これからは、標高だけにとらわれず、自分なりのペースで、胸を張って生きていこうと心に決め、私はその小さな山に別れを告げた。



コメント